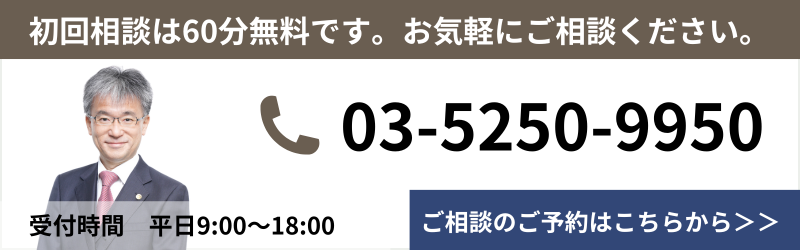遺産分割がスムーズに進まず、相続人間で揉めてしまう要因の典型的なものとして、特別受益と寄与分の問題があります。特別受益と寄与分は、相続人間の実質的な公平を図る観点から、原則的な相続分を修正する制度という点で共通しています。それぞれの制度の概要と、認められた場合の相続分はどのような計算になるのか等ご説明します。
目次
特別受益とは
特別受益とは、一部の相続人だけが被相続人から生前贈与や遺贈、死因贈与で受け取った利益のことです。例えば、相続人のうちの1人が生前に自宅の建築資金を出してもらった、マンションを買ってもらった等といった場合が特別受益に該当します。
このような場合、これを相続財産の前渡しと見なして、特別受益を受けた相続人の相続分を特別受益の分だけ減らすことで、相続人間の公平を図ることが認められています。
例えば、被相続人の遺産が1億円で、相続人が兄弟2人であり、兄だけが生前に2000万円の贈与を受けていた場合、兄への生前贈与(特別受益)を考慮しないと1億円を2分の1ずつ分けることになります。したがって、
兄の相続分:5000万円 (生前贈与2000万円)
弟の相続分:5000万円
つまり、
実質的に兄は7000万円で、弟は5000万円となり、不公平です。
そこで、兄への生前贈与(特別受益)を考慮して計算をします。
特別受益の持戻しの計算方法
生前贈与等で受け取った財産が特別受益にあたる財産であると認められたときは、相続開始時の遺産(相続財産)に特別受益の金額を加算した「みなし相続財産」に基づいて計算します。このように、特別受益の金額を相続財産に加算することを「特別受益の持戻し」といいます。
基本的な計算方法は以下のとおりです。
相続開始時の財産評価額+特別受益の財産評価額=「みなし相続財産」
特別受益者ではない相続人:「みなし相続財産」×法定相続分
特別受益者である相続人 :「みなし相続財産」×法定相続分-特別受益の財産評価額
では、上記に基づいて、もう一度、先の兄弟2人の例について計算をしてみましょう。
みなし相続財産 = 1億円(相続開始時の遺産)+2000万円(兄の特別受益の持戻し) = 1億2000万円
法定相続分はそれぞれ2分の1なので
兄の相続分:1億2000万円 × 1/2 – 2000万円 = 4000万円
弟の相続分:1億2000万円 × 1/2 = 6000万円
となります。これにより
兄の取得した額 4000万円+生前贈与2000万円=6000万円
弟の取得した額 6000万円
となり、公平が図られます。
特別受益とみなされる可能性がある事例
- 相続人の1人が、生前に故人に自宅を買ってもらった
- 相続人の1人が、生前に故人から、自宅の建築資金を出してもらった
- 相続人の1人が、生前に故人から、生活費の援助を受けていた
- 被相続人の預金口座について、当該口座を管理していた相続人の1人による多額の使途不明金の出金があった
上記のようなことがもし事実としてある場合、特別受益とみなされる場合があります。
尚、特別受益の対象となるのは、以下の通りです。
①遺贈
②婚姻や養子縁組のための贈与
婚姻の際の持参金などが含まれます。挙式費用などは一般的には認められません。
③生計の資本としての贈与
特別受益になる「生計の資本」の贈与とは、独立して生活を営んでいる子などへの多額の贈与のことをいいます。例えば、住宅購入資金や事業資金等の贈与が特別受益になります。同居している家族の通常の生活費を負担していても、それは一般的な扶養義務の履行の範囲内であり、特別受益にはあたらないとされます。
どのような場合に特別受益が認められるのかは微妙な判断ですので、納得が出来ない点やご不安な点がある場合、特別受益を巡って、他の相続人と揉めそうな場合は、弁護士にご相談ください。
持戻し免除
生前贈与が特別受益となる場合には、すでに述べたとおり持戻しされます。
しかし、生前贈与などをした被相続人の意思としては、このような持戻しを望んでいないと考えられる場合があります。たとえば、いろいろとお世話になったのでその世話をしてくれた相続人に特別に多くあげたいという場合などです。このような場合に持戻しされてしまうと、せっかくの厚意が無になってしまいます。
このような場合に持戻しをしない旨の意思表示をしておくことで、その特別受益について、持戻ししないとすることが可能です。これを「持戻し免除」といいます。この持戻し免除の意思表示の方法には法律上は特に手続や書式の決まりはありません。しかし、「言った・言わない」の争いを避けるためにも、書面で残しておくことをおすすめします。
特別受益をめぐっては、事後的にトラブルになるケースが少なくなく、遺産分割の調停などでも揉めることが多々あります。もし、被相続人から贈与、遺贈を受けている相続人がいる場合には、弁護士にご相談ください。
寄与分とは
寄与分とは、相続人の中で、被相続人の財産形成または維持に特別の寄与をした者に、法定相続分以上の財産を取得させ、実質的な公平を図る制度です。
例えば、被相続人の遺産が1億円で、相続人が兄弟2人であり、兄が家業を手伝って、被相続人の財産形成に2000万円の寄与があった場合等に寄与分が問題となります。
寄与分の要件
寄与分が認められるためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。
①相続人による「寄与行為」があること
②寄与行為が「特別の寄与」であること
③被相続人の「財産の維持または増加」があり、寄与行為との間に「因果関係」があること
要件①の「寄与行為」については、以下のようにある程度類型化されていますが、認められるかどうかは個別具体的な実質的状況によるところが大きいです。
(1)家事従事型
例えば、被相続人が経営している店を相続人である息子が15年間無給で手伝った場合などです。
(2)出資型
例えば、被相続人に対し家を建てるための土地の購入資金を提供した場合などです。
(3)療養看護型
例えば、5年間にわたって息子が仕事をすることもなく、寝たきりの被相続人を24時間介護し、本来介護職員を雇った場合に発生する支出である200万円を削減した場合などです。
(4)扶養型
例えば、被相続人が病気療養のため、仕事ができない状態で収入がないため、生活費にかかる金額の大半を負担していた場合などです。
(5)財産管理型
例えば、被相続人が所有している賃貸不動産の清掃や手入れなどの管理をしていた場合などです。
要件②の「特別の寄与」ですが、被相続人と相続人の身分関係に通常期待される程度を超えるような特別の貢献である必要があります。寄与分として認められる貢献は通常のものではなく「特別」である必要があります。そのため、夫婦や親子として多少身の回りの世話をした程度の貢献では、特別の寄与として認められません。
要件③のとおり、被相続人の財産の維持または増加に貢献した行為にのみ寄与分は認められます。そのため、いくら被相続人に貢献したとしても、その行為が財産の維持、増加に関わらない場合は寄与分として認められません。
寄与分の計算
寄与分の具体的な計算方法について説明します。
まず、相続財産から寄与分額を除きます。次に、除いた後の額を法定相続分で計算します。
寄与分がある人の相続分:(相続財産-寄与分)×法定相続分+寄与分
寄与分がない人の相続分:(相続財産-寄与分)×法定相続分
例えば、被相続人の遺産が1億円で、相続人が兄弟2人であり、兄が家業を手伝って、被相続人の財産形成に2000万円の寄与があった場合、
みなし相続財産 = 1億円 – 2000万円(兄の寄与分) = 8000万円
兄の相続分:8000万円 × 1/2 + 2000万円 = 6000万円
弟の相続分:8000万円 × 1/2 = 4000万円
となります。
寄与分とみなされる可能性がある事例
- 被相続人である親の家業に従事して、財産を増やした
- 被相続人である夫の事業に、妻が無償で従事していた
- 親の介護をして介護費用の支出を抑えた
このような場合は、寄与分が認められる可能性があります。
ただ、どのような場合に寄与分が認められるのかは非常に微妙な判断を含む場合もありますので、納得が出来ない点やご不安な点がある場合、寄与分を巡って、他の相続人と揉めそうな場合は、是非、お早めに弁護士にご相談ください。
なお、寄与分が認められるのは、法定相続人に限られます。例えば、息子の妻が被相続人の生活費を補填したというような場合には、残念ながら寄与分を主張することはできません。
しかし、法定相続人でないものが、被相続人の療養看護その他の労務の提供をして、被相続人の財産の増加及び維持に貢献していた場合には、「特別寄与料」を相続人に請求することが可能です。
特別寄与料の請求は相続人との協議が前提とされておりますが、協議がまとまらない場合は裁判所に協議に代わる処分を請求することができます。この請求期限は特別寄与者が相続の開始および相続人を知ったときから6か月を経過するまで、又は(相続の開始等を知らなかったとしても)相続開始のときから1年を経過するまでと定められております。
弁護士への相続の相談をご検討されている方へ
相続にはそれぞれの事案ごとに異なった背景事情があり、相続人の方々の想いもそれぞれ異なるものだと思います。ただ一方で、相続の問題は法律問題であり最終的な解決は法律の枠内で行われるものでもあります。
そこで、相続問題のお悩みは法律の専門家である弁護士に、できるだけ早い段階でご相談いただければと思います。遺産分割協議の段階で弁護士に交渉をご依頼いただくことで、比較的短期間で解決ができる可能性が高まり、あなたの貴重な時間が奪われずに済み、またご家族・ご親族間の関係性も悪化させずに済むことが多いです。
上記のような理由から、「遺産分割協議が進まないな」「自分の希望どおりに遺産相続が進められないかもしれない」と少しでも思ったタイミングで弁護士への相続の相談をおすすめしております。
弁護士に相続の相談をするべきタイミングについて>>